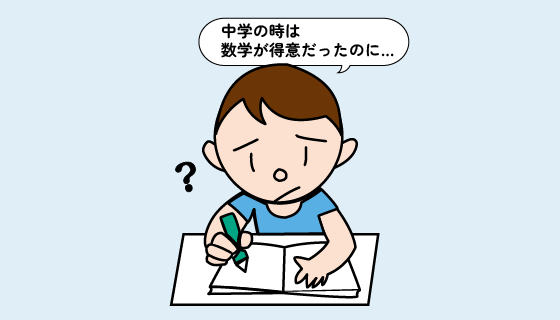中高一貫校 大学受験必勝法②
前回の続き、中高一貫校 大学受験必勝法②をお伝えします。
第二の分かれ道(国公立受験組と私立文系組)
中3の一学期(早いところでは中2の後半)に、高校数学がスタートする。ここで数学が本当の『高等数学』になる。
具体的には数Ⅰの『二次関数』、なかでも『最大最小』『不等式、解の存在範囲』―ここでこれまでの数学のできる、できないがふり出しに戻る。
中学数学の範囲でよくできた生徒群が、ここで2つに割れる。(公立進学校トップレベル校では高1の一学期末におこる)
なぜか?中学数学では、未知数を文字(x,a)で置くが、それは実は手にさわり見ることができる(実体のある数)にすぎない。
数Ⅰの二次関数では、範囲が文字になる。例えば(-2<x<a),このaは決まらない数。aがどの範囲にあるのか、場合分けが必要になる→ここで大混乱
つまり、はじめて体験した『真の代数』を自分のものとできる人とできない人=大学受験を数学で突破できる人できない人に大分解する。
わかりやすく言えば、国公立受験組と私立文系組にきっちり分けられる。